特集「統合失調症の研究最前線」の中の論文です。
松井三枝, 稲田祐奈, 蝦名昂大:統合失調症の認知機能改善療法、精神科、32 (3), 204-210, 2018

専門分野:臨床神経心理学、認知神経科学
特集「統合失調症の研究最前線」の中の論文です。
松井三枝, 稲田祐奈, 蝦名昂大:統合失調症の認知機能改善療法、精神科、32 (3), 204-210, 2018
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所成人精神保健研究部の先生方の協力研究がJournal of Affective Disordersに掲載されることに決まりました。神経心理学的評価法について関与させていただきました。
Narita-Ohtaki R, Hori H, Itoh M, Lin M, Niwa M, Ino K, Imai R, Ogawa S, Sekiguchi A, Matsui M, Kunugi H, Kamo T, Kim Y: Cognitive function in Japanese women with posttraumatic stress disorder: association with exercise habits. Journal of Affective Disorders (IF 3.786), in press.
金沢大学脳神経外科との共同研究(awake surgeryにおける高次脳機能研究)がFrontiers in Behavioral Neuroscienceに掲載が決まりました!術中課題や神経心理評価法について関与させていただきました。
Nakajima N, Kinoshita M, Okita H, Yahata T, Matsui M, Nakada M: Neural networks mediating high-level mentalizing in patients with right cerebral hemispheric gliomas. Frontiers in Behavioral Neuroscience,12, 2018, https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00033. (IF 3.138)
日本心理学会のシンポジウムでの内容が母体となった一般向けの本です。
松井三枝・井村修(編)日本心理学会(監修)、「病気のひとのこころー医療のなかでの心理学」、誠信書房、2018.1、ISBN978-4414311204
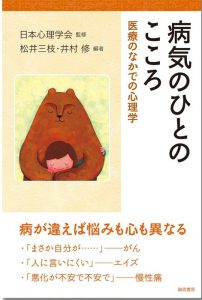
内容説明
「患者のこころのありよう」はその抱える疾患や重症度によってさまざまであり、それぞれの特徴を理解したきめ細やかなアプローチが求められる。本書では身体疾患から精神疾患まで幅広くとりあげ、医療現場にある心理職の活動にも言及しながら、患者のこころを理解するヒントと基礎知識を提供する。
目次
編者はじめに
第1章 痛みをもつこころと援助
第2章 透析患者のこころの理解
第3章 筋ジストロフィーの人のこころと援助
第4章 エイズになることとその援助
第5章 がんの人のこころとその援助
第6章 がんの治療を受ける子どもをいかに支えるか
第7章 周産期医療とこころの支援――妊娠・出産・赤ちゃんの育ちをめぐって
第8章 認知症者の脳とこころ――神経心理学的アプローチ
第9章 脳にダメージを受けた方たちのこころとその支援
第10章 精神の病と脳のはたらき――統合失調症を中心に
編者おわりに
執筆者
松井三枝【編者はじめに、第10章】
有村達之【第1章】
服巻 豊【第2章】
井村 修【第3章、編者おわりに】
井村弘子【第4章】
小池眞規子【第5章】
佐藤聡美【第6章】
橋本洋子【第7章】
小森憲治郎【第8章】
山口加代子【第9章】
2017年の認知神経科学会での「シンポジウム神経心理学的検査」で発表した内容が論文として掲載されました。意味性認知症の症例による神経心理学的アセスメントを紹介し、その意義を考察したものです。
稲田研究員がまとめてくださった周産母子センターとの共同研究で下記の題目の論文が北陸心理学会誌「心理学の諸領域」に受理されました。
掲載2017年12月2日
稲田祐奈,松井三枝,川崎裕香子,吉田丈俊: 低出生体重児における発達特性の検討:Bayley乳幼児発達検査第3版(Bayley-Ⅲ)を用いて、心理学の諸領域、6、41-48、2017.
富山大学和漢医薬学総合研究所神経機能学分野 東田千尋教授との共同研究が雑誌Nutrients(IF=3.550, 2016; 5-year IF=4.187, 2016)に受理されました。研究の内容は、山芋エキス(ジオスゲニン)摂取が認知機能に影響を及ぼすかどうかの検討になります。
Toda C, Yang X, Matsui M, Inada Y, Kadomoto E, Nakada S, Watari H, Shibahara N: Diosgenin-rich yam extract enhances cognitive function: a placebo-controlled, randomized, double-blind, crossover study of healthy adults. Nutrients, 9(10), 1160; doi:10.3390/nu9101160, 2017.
Sakai T, Komaki Y, Hata J, Okahara J, Okahara N, Inoue T, Mikami A, Matsui M, Oishi K, Sasaki E, Okano H: Elucidation of developmental patterns of marmoset corpus callosum through a comparative MRI in marmosets, chimpanzees, and humans. Neuroscience Research, 122, 25-34, 2017.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168010217301025
マーモセット、チンパンジー、ヒトの脳梁の発達を比較
家族で養育を行う霊長類は乳児期から子ども期にかけて神経の成熟が著しい
脳梁は左右の大脳半球を結ぶ最大の神経線維の束白質路であり、感覚、運動、認知などの多様な神経機能と関連しています。金沢大学国際基幹教育院の松井三枝臨床認知科学教授らはヒトの脳梁発達研究を行ってきました。この度、酒井朋子 ジョンズ・ホプキンス大学海外特別研究員を中心とする慶應義塾大学、ジョンズ・ホプキンス大学、中部学院大学の霊長類研究者と共同で研究グループをくみ、世界で初めてマーモセットの脳梁を真横から見た断面積がどのように発達していくのか、その過程を明らかにしました。調査の結果、マーモセットでも、チンパンジーやヒトと同様に、乳児期に脳梁の断面積は急速な成長を見せ、その後ゆっくりと変化することがわかりました。一方で、母親以外の家族も子育てに参加するマーモセットとヒトは、養育期に母親と子どもの密接な関係が続くチンパンジーと大きく異なりました。マーモセットとヒトでは、チンパンジーよりも、乳児期後半から子ども期にかけて、脳梁の断面積が大きく増加することが明らかとなりました。特に、マーモセットの脳梁の断面積は大きく成長することがわかりました。これらの脳梁の発達の違いは、人類進化に伴う養育や社会行動の進化的変化と関連していることが示唆されました。論文は2017年9月1日、Neuroscience Research誌に掲載されました。
Tsuzuki, D., Homae, F., Taga, G., Watanabe, H., Matsui, M., & Dan, I. Macroanatomical landmarks featuring junctions of major sulci and fissures and scalp landmarks based on the international 10-10 system for analyzing lateral cortical development of infants. Frontiers in Neuroscience, section Evolutionary Psychology and Neuroscience, 11, 394, 2017, doi: 10.3389/fnins.2017.00394
チンパンジーの脳梁の発達様式を明らかに:
ヒト特異的な言語、数概念に関わる神経連絡の成熟では乳児期が鍵となる
脳梁は大脳半球を結ぶ最大の白質路であり、感覚、運動、認知などの多様な神経機能と関連しています。金沢大学国際基幹教育院の松井三枝臨床神経心理学教授らはヒトの脳梁発達研究を行ってきました。この度、酒井 朋子 ジョンズ・ホプキンス大学海外特別研究員(元霊長類研究所大学院生、研究員)、三上 章允 中部学院大学教授(元霊長類研究所教授)、鈴木 樹理 霊長類研究所准教授、宮部-西脇 貴子 霊長類研究所助教、友永 雅己 霊長類研究所教授、濱田 穣 霊長類研究所教授、松沢 哲郎 京都大学高等研究院教授、岡野 栄之 慶應大学教授、大石 健一 ジョンズ・ホプキンス大学Associate Professorと共同で研究グループをくみ、世界で初めてチンパンジーの脳梁の正中断面積の発達過程を明らかにしました。その結果、脳梁の上方に位置し、行動制御、言語記憶、数概念に関わる脳梁吻側体部(rostral body)において、ヒトでは乳児期にチンパンジーよりも大きく増加することが見出されました(図4)。一方、脳梁の前方に位置し、注意制御に関わる脳梁吻(rostrum)において、チンパンジーでは子ども期にヒトよりも大きく増加することが明らかとなりました(図4)。この研究成果は、2017年6月27日(アメリカ東部標準時間)に、PLOSONEの中で報告されました。
概要1
私たちヒトの脳が生後初期にどのように成長するのかを理解することは、神経科学や人類学の分野では、重要なトピックの一つです。また、ヒトとヒト以外の霊長類における脳構造の発達様式を比較することは、ヒトの高次脳機能の進化的変化を紐解くうえで欠かせません。
本研究では、脳梁の正中矢状面の発達様式に着目しました。脳梁は大脳半球を結ぶ最大の白質路であり、全ての哺乳類にあります。脳梁は、脳領域間の神経連絡のトポロジーを表現し、感覚、運動、認知などの多様な神経機能と関連しています。よって、脳梁の発達を調べることで、各脳領域の神経連絡の成熟過程を推定することができます。
先行研究から、ヒトでは、脳梁の正中矢状面が乳児期の急速に拡大し、それ以降比較的ゆっくりとした変化を示すことが報告されています。一方、チンパンジーでは、出生後6歳~54歳(子ども期~老年期)の個体を対象とした横断的磁気共鳴画像(MRI)研究により、脳梁の正中矢状面が子ども期から成体期にかけてゆっくりと変化することが報告されていますが、乳児期に関する発達はまだ調べられていません。この横断的研究による知見を確証するためには、生後6歳以前(子ども期以前)のチンパンジー個体を対象とした縦断的研究を行う必要がありました。
そこで、本研究では、4個体(アユム、クレオ、パル、ピコ)の子どもチンパンジーを対象に、MRI法を用いて、出生後1.8ヶ月~6歳(乳児期~子ども期)の脳梁の正中矢状面における7領域(図1、2)の発達的変化を縦断的に追跡しました。その結果、チンパンジーの脳梁全体は、ヒトと同じように、乳児期に急速に拡大し、子ども期にはゆっくりと変化することが見出されました(図3、4)。
その一方で、チンパンジーとヒトにおける大きな違いもありました。一つは、脳梁の上方に位置する脳梁吻側体部(rostral body)において、ヒトでは乳児期にチンパンジーよりも大きく増加することが見出されました(図4)。二つ目は、脳梁の前方に位置する脳梁吻(rostrum)において、チンパンジーでは子ども期にヒトよりも大きく増加することが明らかとなりました(図4)。
rostral body は内側前頭前皮質と前運動皮質を結ぶ神経線維の投射を受け、行動制御、言語記憶、数概念に関わることが報告されています。一方、rostrumは眼窩前頭皮質と背外前頭前皮質を結ぶ神経線維の投射を受け、注意制御に関わることが報告されています。つまり、チンパンジーとヒトにおけるrostral bodyとrostrumの発達の違いは、人類進化に伴う脳システムの進化的変化と関連していることが示唆されました。
http://neuropsychol.w3.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/figuresPLOSONE2017627.pdf
書誌情報
【DOI】10.1371/journal.pone.0179624
Tomoko Sakai, Akichika Mikami, Juri Suzuki, Takako Miyabe-Nishiwaki, Mie Matsui, Masaki Tomonaga, Yuzuru Hamada, Testuro Matsuzawa, Hideyuki Okano, and Kenichi Oishi. (2017) Developmental trajectory of the corpus callosum from infancy to the juvenile stage: comparative MRI between chimpanzees and humans. PLOSONE, 1-22.